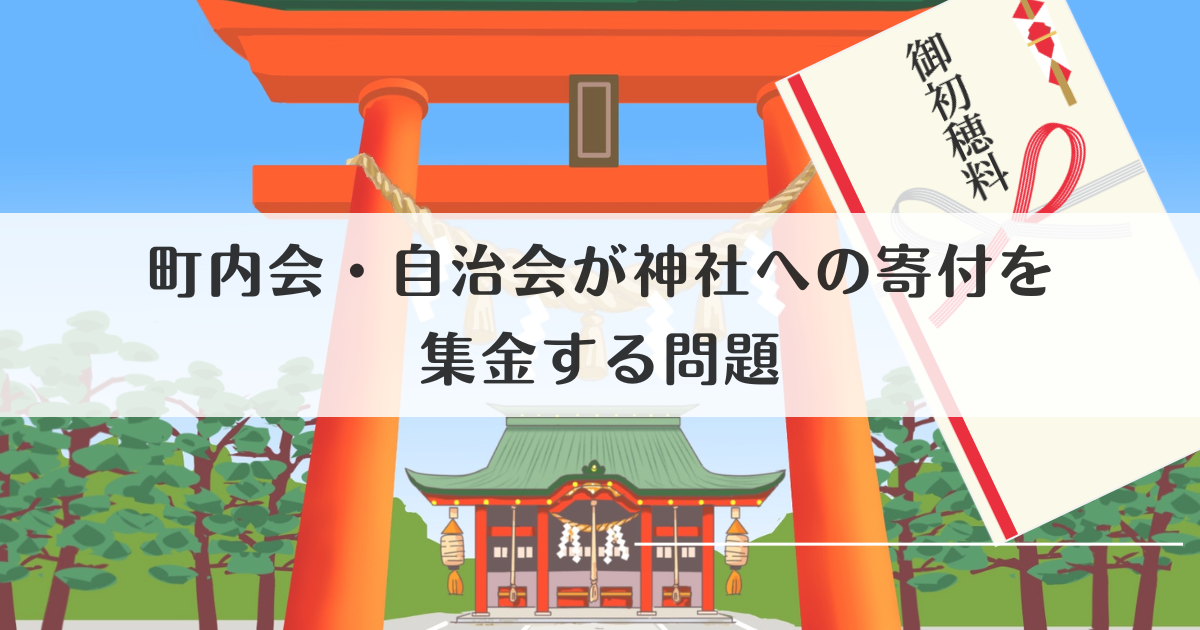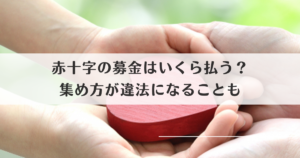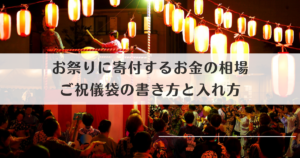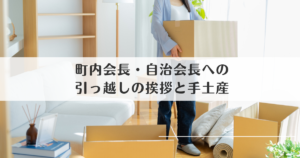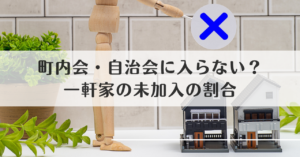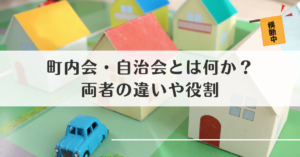神社は恋愛や仕事、学業、安産などを祈願したり、観光で訪れる場所だったりして、日本人には文化として根付いています。
ただ、町内会・自治会と神社との関係には賛否両論あり、特に初穂料や神社費といったお金に関わることになると問題が大きくなり、裁判にまでなったケースがあります。
実際にヒラリが町内会長として、町内会や学区で経験した町内会・自治会と神社、特にお金のことについてお伝えします。
町内会・自治会が神社の寄付を集金する理由
みなさんが住んでいる地域に神社、いわゆる地元に氏神様がある場合、昔から町内会・自治会が神社を管理していることが多くあり、町内会・自治会が神社のお祭りを開催したり、毎月清掃をしたり、悪くなったところを修繕したりして、神社を守っています。
神社を守るためには、お金が必要になるため、町内会・自治会が神社への寄付を集金する必要が出てきます。
※神社への寄付のことを初穂料と言うこともあります。
 ヒラリ
ヒラリヒラリの町内にある神社は神社庁に所属していますが「村社」(村の神社)となっており、昔から町内会が管理してきました。
町内会・自治会が神社の寄付を集金することの問題点
町内会・自治会が神社への寄付を集金することで問題になるのは、「神社は神道という宗教(神社本庁の公式サイトで民族宗教と記載があります)なので、一宗教のために、町内会・自治会が集金するのはいかがなものか?」ということです。
神道は、日本の民族宗教といわれ、日本人の暮らしにとけ込んでいます。
引用元:神社本庁の公式サイト|神道とは
初詣や七五三など、神社は日本人の文化に根付いているとは言え、町内会・自治会には、神道以外の宗教を信仰している人がいます。
そのため、「町内会・自治会が神社への寄付を集金するのは問題がある」と思う人がいるのは不思議ではありません。
町内会・自治会と神社の関係について、ヒラリが記事を作成していますので、ご覧ください。


神社への寄付の集金方法を考える必要あり
昔から続いてきた神社の伝統を守ることは大切ですし、それにはお金がかかるのも事実です。
神社へ寄付をすること自体が嫌な人もいますが、「神社へ寄付はしてもいいけど、神社に町内会・自治会が関わっていること、神社への寄付を町内会・自治会が集金していることが嫌」という人も多くいます。
さらに町内会・自治会の班長・組長や神社の役員になって、それぞれの家に集金に行くのも負担になります。
町内会・自治会と神社を完全に切り離して、神社の氏子(氏神様を信仰している人)を中心に集金を行う、百歩譲って、町内会・自治会が寄付を集金するにしても、あくまでも寄付の希望者のみが寄付できる仕組みを作る必要があります。
町内会・自治会として手間がかからないように、町内会・自治会の会費から神社へのお金を一括で集金するのは、違法という判例があります。詳しくはこのページ内の「町内会・自治会と神社のお金に関する裁判の判例」をご覧ください。
どちらにしても、「寄付は希望者のみ」、「寄付の金額は自由」ということを徹底しなければいけません。



ヒラリの町内会では、町内会と神社が奉賛会という別組織になっており、寄付は希望者のみで寄付の金額は自由です。集金は奉賛会が行い、町内会は関与しないようになっています。
町内会・自治会にはやむを得ない事情も
一方、神社への寄付で悩んでいる町内会・自治会もありますので、現役の町内会長という立場からその事情をお話させてください。
地元の神社(氏神様)ではなく、以下のように、もう少し広い範囲にある神社の寄付(初穂料とも言います)の集金を行っている町内会・自治会もあります。
- ◯◯区にある神社
- ◯◯市にある神社
- ◯◯県にある神社
ここでは神社名は出しませんが、これら地元以外にある神社から町内会・自治会に毎年「寄付を集めてください」というお願いが来ます。
地元の神社への寄付は主体的に行っている町内会・自治会も、これらの神社からの寄付のお願いには、「本当は断りたいけど今までもやってきたら」という理由で、仕方なく集金していることもあります。
地元の神社への寄付の集金にプラスして、他の神社もあると1年間に何度も寄付を集金することなって、役員が疲弊している町内会・自治会もあります。



ヒラリの町内会が所属する地域連合会にも、3つの神社(学区以外の場所にある神社)から寄付のお願いがあります。地域連合会として、このお願いを断ることを検討することもありますが、昔から継続してやっていることなので、断りづらい状況にあります。
町内会・自治会と神社のお金に関する裁判の判例
町内会・自治会と神社のお金に関する裁判である2002年(平成14年)4月の佐賀地裁(判例)、2023年3月の京都地裁(和解)について、まとめました。
2002年(平成14年)4月の佐賀地裁(判例)
自治会費と神社の費用を一括徴収する方法について、2002年(平成14年)4月に佐賀地裁で行われた裁判での「神社神道を信仰しない自治会員の信教の自由を侵害し違法である」という判例があります。
自治会費に含まれる特定宗教関係費(神社関係費)の支払を拒絶した自治会員に対して自治会員としての取扱をしなかった自治会の行為は、神社神道を信仰しない自治会員の信教の自由を侵害し違法であるとして、自治会員の地位確認請求が認容されたが、不法行為による慰藉料請求は棄却された事例(佐賀地裁平成14.4.12判決)
引用元:レファレンス協同データベース|レファレンス事例詳細
この裁判に関して、新潟市の「第4章 自治会・町内会のよくあるQ&A」でも、町内会・自治会の運営者に以下のように注意喚起しています。
■氏子会費に関する裁判事例 (H14.4.12 判決)
引用元:新潟市|第4章 自治会・町内会のよくあるQ&A
・神社が宗教性を持つことは否定できない。
・神社への支出(氏子会費)も、宗教上の行為への参加を強制するものであると認められる。
・神社への支出は信教の自由を侵害するものとして、民法の趣旨に照らして違法な行為である。
2023年3月の京都地裁(和解)
京都三大祭りの1つである「時代祭」というお祭りの行列費用を自治会から支出していたことが問題になり、裁判にまで発展し、2023年3月に京都地裁で、「今後は自治会費からの支出を取りやめる」ということで和解しました。
京都の時代祭に対する自治会費からの支出が問題となった京都地裁での訴訟でも今年3月、今後は自治会費からの支出を取りやめることで住民と自治会の和解が成立した。
引用元:中日新聞|自治会費から神社費支出「信教の自由」に反する? 持続可能なあり方とは
この裁判は地元の氏神様が対象ではなく、有名な京都の平安神宮の時代祭も「神道の宗教行事」ということになり、注目が集まりました。
自治会は今後、時代祭を含む宗教行事へ費用を支出しない。
引用元:産経ニュース|京都・時代祭めぐり訴訟が和解 自治会費から支出なしに
佐賀地裁と京都地裁の裁判の判例や和解のように町内会・自治会と神社の関係、特にお金については、厳しく見ていく必要があります。
この記事のまとめ
今回は、ヒラリの町内会長としての経験から、町内会・自治会と神社のお金の関係についてお伝えしました。
佐賀地裁と京都地裁の裁判の判例や和解例のように、町内会・自治会の会費から神社の行事や運営に支出することは、よくありません。
町内会・自治会と神社を完全に別組織にして、住民のみなさんが気持ちよく寄付ができる環境作りが必要です。