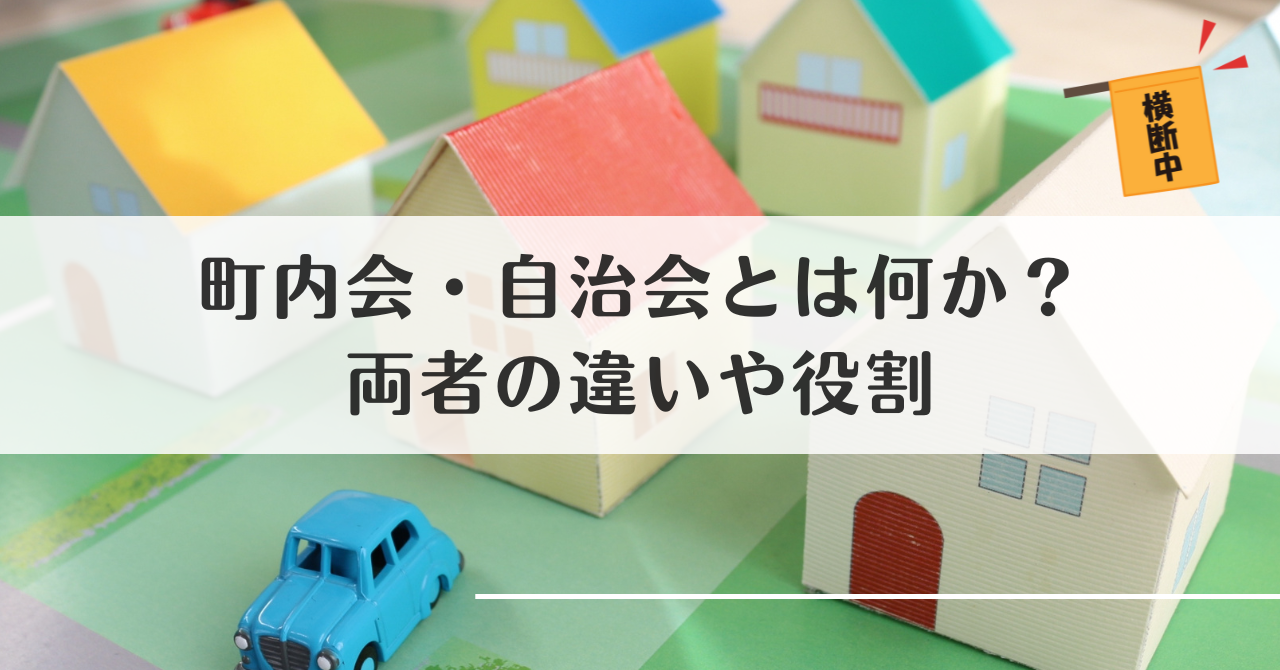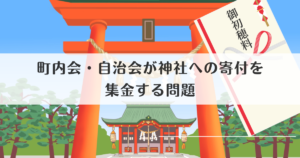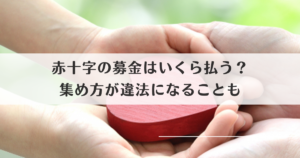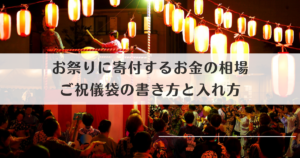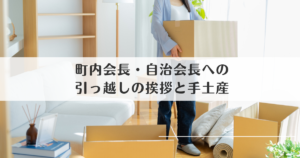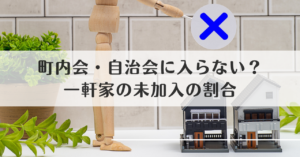自分が住んでいるところに町内会・自治会があることは知っているけど、「町内会・自治会って具体的に何をしているの?」と疑問に思ったことはありませんか?
今回の記事では、現役の町内会長であるヒラリが今までの経験や実体験を元に「町内会・自治会とは何か?」「町内会と自治会の違い」「町内会・自治会の運営者」についてお伝えします。
 ヒラリ
ヒラリこのページの内容について、みなさんの町内会・自治会の情報を募集しています。詳細は「町内会・自治会の情報募集」をご覧ください。
町内会・自治会とは何か?役割を簡単に説明します
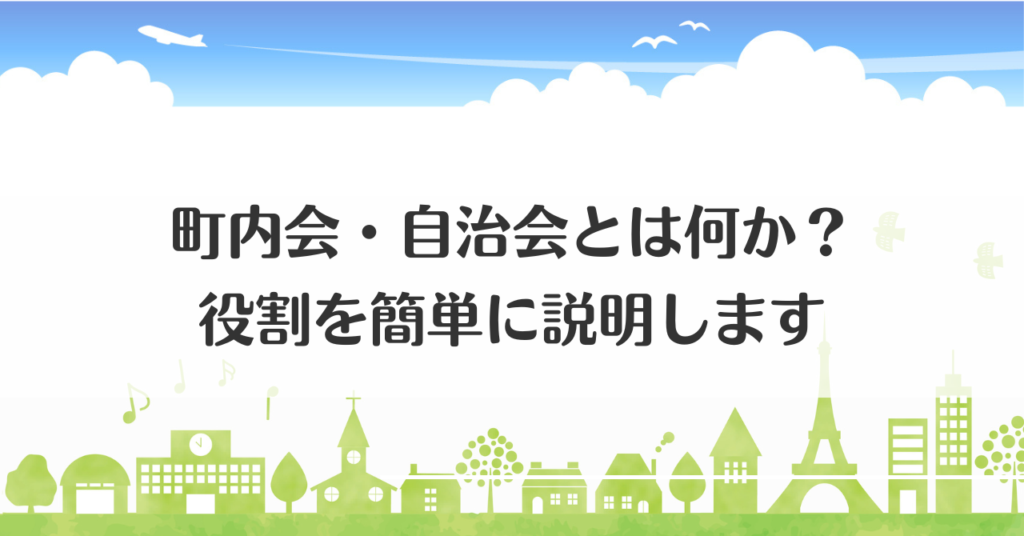
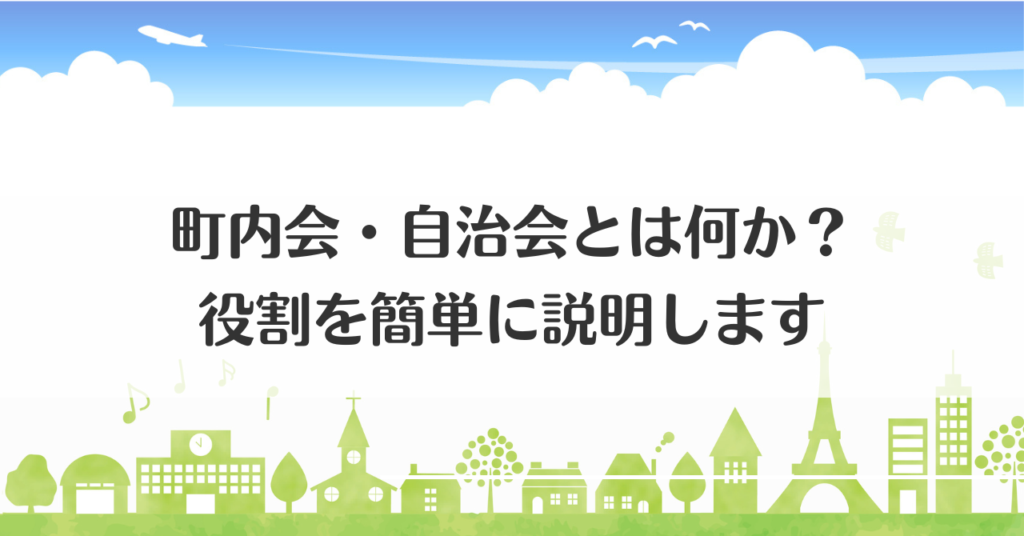
町内会・自治会と言っても、地域によって仕組みや役割が違いますが、ここでは、一般的な町内会・自治会の役割をお伝えします。
簡単に一言で言いますと、町内会・自治会とは、町内に住んでいる人たちの住みやすさや安全を守る組織です。
町内会・自治会の役割は大きく分けると次の5つあります。
市区町村からの情報を住民に伝える
町内会・自治会には、市区町村から発信される情報を町内の人たちに伝える役割があります。
回覧板を使って市区町村からの情報を町内に回している町内会・自治会もありますし、新しく開発されたエリアでは、デジタル化(LINEなどで情報共有)している町内会・自治会もあります。
例:ゴミの収集日や回収方法の情報
ゴミの収集日のスケジュールやゴミの回収方法が変更になったときのお知らせがあります。
特に年末年始はゴミの収集日が異なるため、特別に市区町村から回覧する書類が出ることがあります。
例:イベント情報
夏祭り(盆踊り)や運動会などのイベント情報が町内に回覧されることによって、イベントに参加しやすくなります。
町内会・自治会として市区町村のイベントに参加することもあり、町内だけでなく、同じ市区町村の住民として交流ができます。



ヒラリの町内会では、紙ベースの資料を回覧板を使って町内に回していますが、今後はデジタルを取り入れることも検討しています。
防犯活動


町内会・自治会は、町内に住む人たちの安全を守る活動をしています。
防犯パトロール
例えば、夏休みや年末年始に防犯パトロールをして、危険箇所を発見したり、不審者が気軽に町内に入れないようにします。
市区町村ではなく、町内会・自治会独自で防犯カメラや防犯灯(街路灯)を設置しているところもあり、これらの設備は犯罪抑止になり、町内会・自治会の安全性を高めます。



ヒラリの町内会では、町内会で防犯カメラと防犯灯を設置しており、町内で何か不審な出来事が起きたときには、警察に映像を確認してもらっています。
交通当番
町内会・自治会として、子どもたちが安全に学校に通えるよう通学路の危険箇所を見つけて、市区町村や学校に改善をお願いしたり、登校時に大きな交差点で交通当番(旗振り当番)をします。
交通当番は子どもたちを危険から守るという意味もありますが、子どもたちと挨拶をすることによって、お互いに顔見知りになるため、もし不審者が子どもたちに声をかけている時に助けることもできます。



ヒラリの町内会が所属する学区としての活動で、毎月「0」の日に小学生の登校時に交通当番があります。
防災活動


災害はいつどこで起こるかわからないため、日頃から防災訓練を行い、備えることが大切です。
町内会・自治会では、災害時の訓練や防災用品の備蓄をしています。
避難訓練
大規模な地震や災害を想定して避難訓練を行い、町内の人たちが実際の避難経路を確認しながら、避難場所(主に学校や公園)に避難する練習をします。
避難訓練をすることによって、実際に災害が起きた時にパニックにならず、冷静に行動することができ、被害を最小限に抑えることができます。
避難所開設訓練
実際に避難者が避難場所(学校や公園)に避難してきたときを想定して、避難所開設訓練をします。
避難所開設訓練では、学校の体育館や公民館を1世帯ごとに分ける練習をしたり、仮設トイレの設置、発電機の使い方など、避難場所で多くの人が生活できるための訓練をして災害に備えます。



ヒラリのところでは、年に1回、学区(小学校の通学を認める範囲)で、防災訓練を行い、災害用仮説トイレの設置、地下式給水栓の使い方、水のうの作り方、簡易担架の作り方、心肺蘇生の練習を行ったりしています。
災害時の情報伝達訓練
大規模な地震や災害を想定して、市区町村と直接連絡が取れる防災無線の使い方を練習したり、町内会・自治会の掲示板やSNSなどを活用して、町内の人たちに情報を伝える訓練もあります。
デジタル化ができれば、町内の人たちに一斉に情報を伝えられますが、災害時には携帯が使えなくなる可能性があり、さらに高齢の方も多い場合は、日頃から人と人との繋がり強くすることも大切です。



ヒラリの地域では、9月1日の防災の日に市の発信で、役員の連絡網を使った情報伝達訓練を年に1回、行っています。
防災用品の備蓄
町内会・自治会によっては、会合場所である集会所や公民館に、水や食料、医薬品などの防災用品の備蓄をして、災害時に町内の人たちが一時的に避難できるようにしています。
災害時には国や市区町村からの援助がありますが、それまでに数日間は町内会・自治会で住民を支えなければいけません。
防災用品にはお金がかかりますし、定期的な入れ替えもあり、管理が大変ですが、いざというときの安心に繋がります。



ヒラリの町内会では、防災用品を備蓄できていないため、少しずつ防災用品のための資金を貯めている最中です。
ハザードマップの作成と配布
ハザードマップとは、災害が発生したときの避難場所や危険箇所がまとめられている地図のことです。
市区町村がハザードマップを作成して、各町内会・自治会に配布することもありますし、町内会・自治会が自分たちの町内専用のハザードマップを作成することもあります。
ハザードマップには以下のような種類があります。
- 洪水ハザードマップ(風水害)
- 火山防災マップ(火山噴火)
- 地震防災マップ(地震災害)
- 液状化被害想定図(液状化災害)
- 津波災害予測図(津波や高潮)
ハザードマップで自分の町内会・自治会にどういった危険があるかを知るのも大切です。



ヒラリの町内会では、市が作成してくれたハザードマップを回覧で回したり、防災訓練で配布したりしています。
清掃活動
町内会・自治会では、町内の道路や公園、河川敷など、町内の人たちが一緒に清掃することによって、町内をきれいにすると同時に、町内に人たちの交流を深めています。
自分たちで清掃することによって、町内をよりきれいに保とうという意識も高まります。



ヒラリの地域では、市が年に1回清掃活動キャンペーンを実施していて、学区が主催し、それぞれの町内会が参加しています。
清掃活動には町内会の人全員ではなく、10名程度の代表者だけが参加し、町内を歩きながらゴミを拾います。
イベントの企画と実施


町内会・自治会では役員が中心となって、イベントの企画をして、町内に住む人たちで開催します。
町内会・自治会でイベントや行事をするメリット
町内のみんなが集まってするイベントは、町内の人たちの交流を深めるいい機会です。
日常ではすれ違いの人たちも、イベントに参加すると世間話をしたり、情報交換をしたりして、信頼関係を築くことができます。
新しく町内に引っ越ししてきた人が、元々住んでいる人たちに溶け込みやすくなるということもあります。
主なイベント
地域によってイベントは異なりますが、主に夏祭り(盆踊り)や花火大会、運動会、フリーマーケット、バーベキュー、焼き芋大会など、子どもから大人まで楽しめるイベントがあります。
町内に神社があるところでは、お神輿を担いで練り歩きをしたり、境内に出店を出したりします。
イベントを開催すると町内の人たちにとって楽しい思い出になりますが、役員に負担がかかるため、役員がやりやすいイベントを企画することも大切です。



ヒラリの町内会ではイベントを開催していませんが、学区として夏祭り、運動会、焼き芋大会が年に1回ずつ開催されていますので、ヒラリの子どもたちは毎年これらのイベントを楽しみにしています。
町内会と自治会の違い
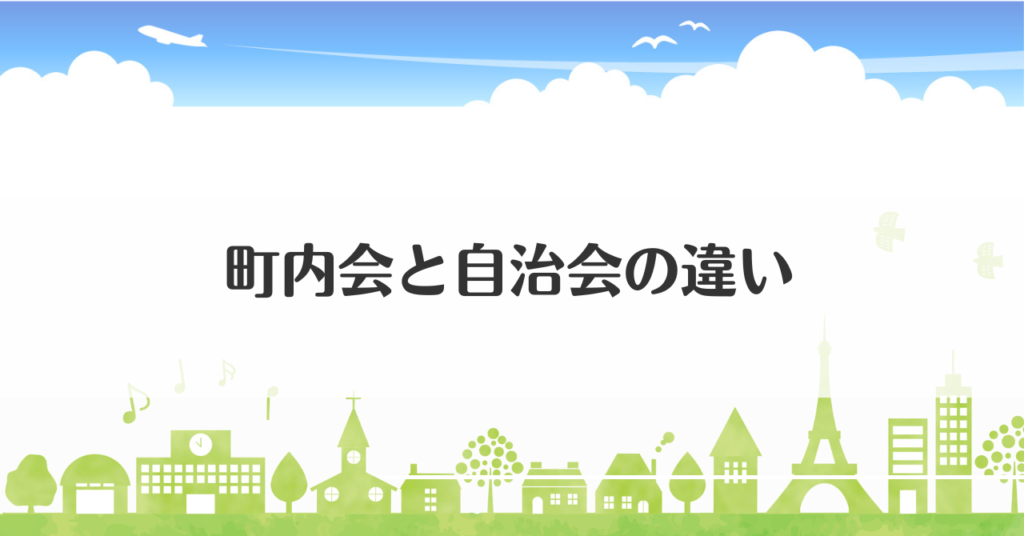
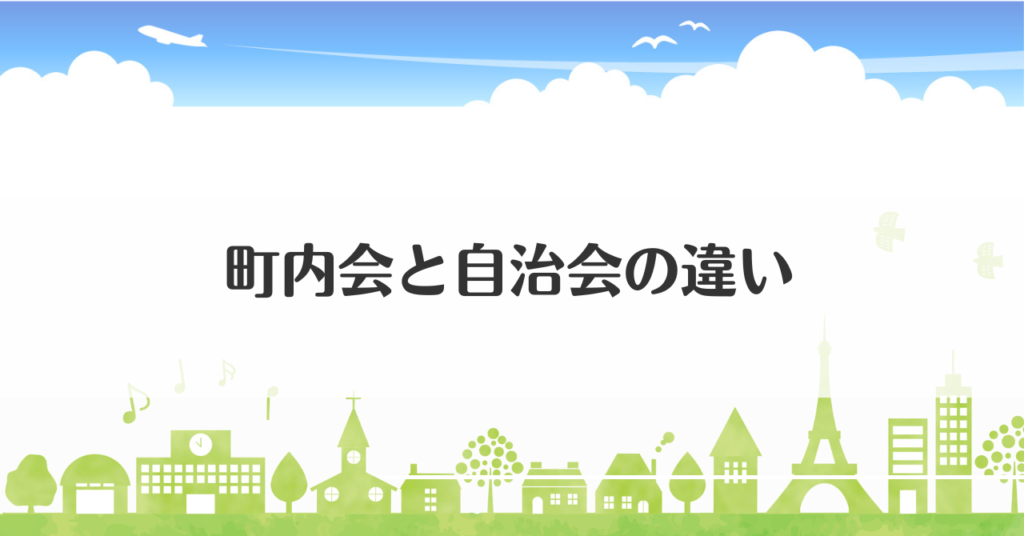
ヒラリはよく「町内会と自治会は何が違うの?」と聞かれることがあります。
ヒラリの町内会が所属する学区では、戸建てが集まるところは「町内会」、大きなマンションは「自治会」と呼んでいます。
ただ、実際には町内会と自治会は呼び名が異なるだけで、基本的には同じ組織ですが、地域によっては町内会と自治会が別々にあり、それぞれが独自の活動をしているところもあります。
ちなみに自治会は「じちかい」と読みます。
令和6年3月に総務省の自治行政局行政課が発表した「地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果」によると町内会・自治会の呼び名は以下のようなものがあり、その内訳も公表されています。
| 区分 | 団体数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 自治会 | 130,569 | 41.1% |
| 町内会 | 67,329 | 22.8% |
| 区 | 34,735 | 11.7% |
| 町会 | 17,882 | 6.0% |
| 部落会 | 4,218 | 1.4% |
| 区会 | 2,731 | 0.9% |
| その他 | 38,374 | 13.0% |
| 合計 | 295,838 | 100.0% |
ヒラリのイメージでは、「町内会」と呼んでいる地域が多いと思ったのですが、実際に「自治会」と呼んでいるところが40%以上もありました。
「地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果」には記載がありませんが、町内会・自治会の他の呼び方として、地縁団体、地域振興会、常会、地域会、地区会、隣組などもあります。
町内会・自治会のエリアはどうやって決めている?
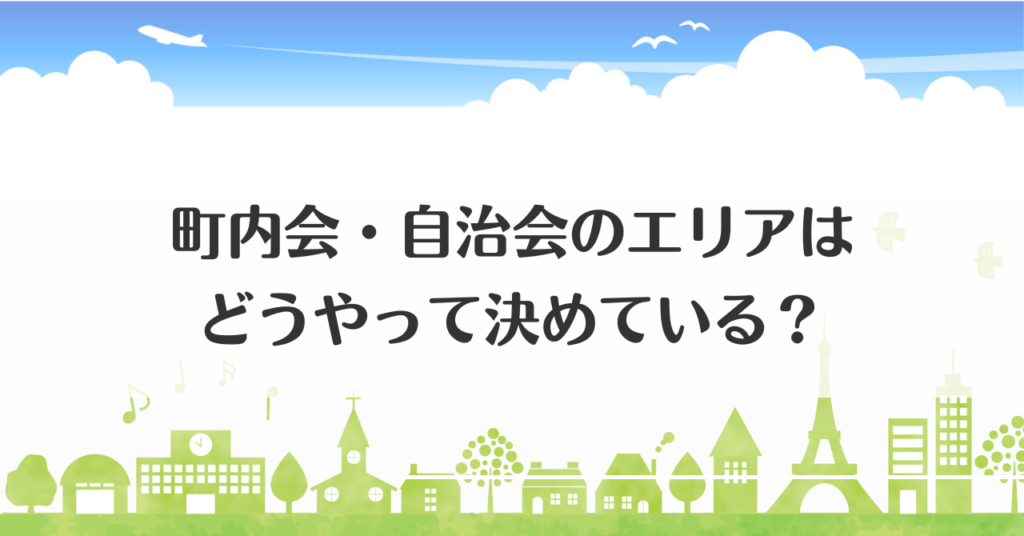
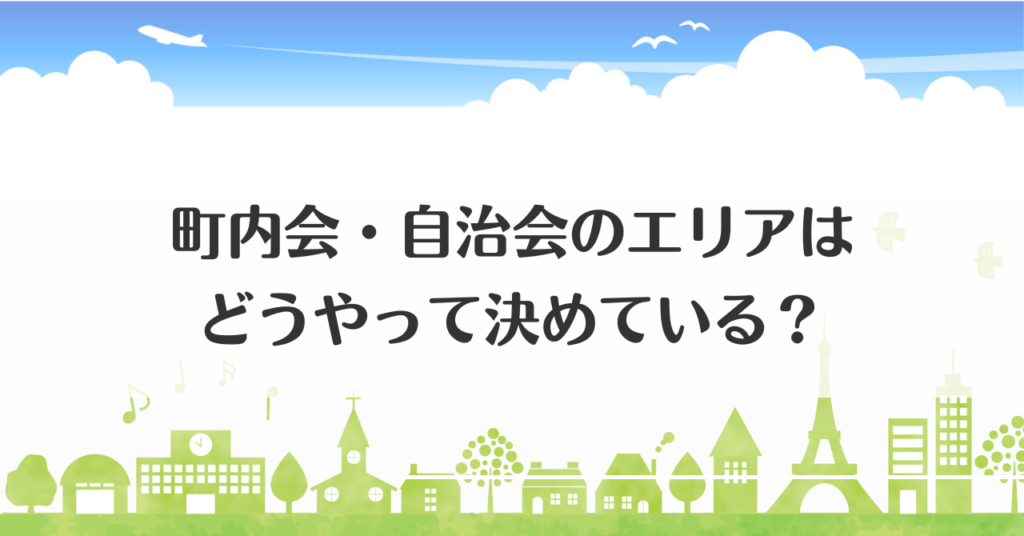
町内会・自治会のエリアは、大きな通りで囲まれたブロック、住民の人数、住民の生活パターンなどによって決められます。
あまりにも広いエリアだと町内会・自治会としての活動が難しくなるので、住民が無理なく活動できるようにします。
1つの小学校や中学校の学区が1つの町内会・自治会になったり、ヒラリの町内会のように小学校の学区の中に複数の町内会がある場合もあります。
戸数にもよりますが、同じ時期にたくさんの住宅ができる場合、1つの町内会・自治会ができることがあったり、大きなマンションが建設される場合は、1つのマンションで1つの町内会・自治会ができることもあります。
町内会・自治会とは、住民の安全を守ったり、住みやすくすることが主な役割のため、近いエリアで1つの町内会・自治会となっていることが多くあります。



ヒラリの地域では、大通りで町内会を区切ったり、マンションごとに町内会・自治会があります。
町内会・自治会を運営する人はボランティア


町内会・自治会は、同じ町内やエリアに住む人たちが協力して運営されています。
町内会・自治会には、ヒラリのような町内会長をはじめ、副会長、会計、会計監査、防犯委員、防災委員、保健委員などの役員がいて、一部で謝礼が発生することもありますが、基本的にはボランティアです。



ヒラリは町内会長として無償のボランティアでやっています。
仕事を定年してから町内会・自治会の役員になる人もいますが、中には「自分の仕事を抱えながら」「子育てをしながら」「家族の介護をしながら」など、忙しい中、町内のためにボランティアで活動している人もいます。
毎年、町内会・自治会の役員が代わるところ、次の人と代わるまでずっと役員をするところもあります。
今の時代、「町内会・自治会に入りたくない」という人が多いのですが、その主な理由が「役員をやりたくない」というものです。
若い世代の多くが共働きで、高齢になっても仕事をしている人が多い中、町内会・自治会のようにボランティアで何かをするということは難しい時代になっています。
そんな中、「少しでも町内のために役立ちたい」と思っている人が、ボランティアで町内会・自治会を支えています。



ヒラリの町内会には任期がありますが、昔から続く町内会のため特別な理由がない限りは、ヒラリを含め、多くの人が長い間ずっと町内会の役員をしています。
この記事のまとめ
町内会・自治会は、町内の住みやすさや安全を守る活動をしています。
主な活動は5つあります。
- 市区町村からの情報を住民に伝える
- 防犯活動
- 防災活動
- 清掃活動
- イベントの企画と実施
町内会と自治会は基本的に同じ意味で使われますが、地域によってはそれぞれ別々の役割を担っているところもあり、町内会・自治会のエリアは、大きな通りで囲まれたブロックや住民の生活パターンなどによって決められていることが多いです。
町内会・自治会の運営は、その地域住んでいる人たちのボランティアで成り立っています。



このページの内容について、みなさんの町内会・自治会の情報を募集しています。詳細は「町内会・自治会の情報募集」をご覧ください。